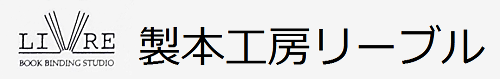「MOMENTUM」の記事を日本語訳で(’17/03/14)
佐藤敦子さんが「MOMENTUM」の英文記事を
日本語に翻訳してくれました。
PDFファイルはこちら。
思い出を修復する―日本の書籍修復の達人
ジョージ・櫻井 2017年2月17日
本の中には何があるのだろう? 職人、岡野暢夫は、父の大切な思い出を修復したいという息子の依頼を引き受ける。
東京にある隠れた穴場のような場所の多くがそうであるように、書籍修復の達人、岡野暢夫の工房
は、大都会の地味な片隅の、地味なビルの中にひっそりとある。
日本の名もないオフィスビル―名もないことで知られるサラリーマンたちのように―それはしばしば魅力的な驚きの宝庫だ。個性はひけらかさない。ぱっとしない外観によって守られているのかもしれない。
岡野さんの工房、リーブルのそのぱっとしないドアを思い切って開ける。金属のドアノブのカチャ
ッという安つぱい音。そしてそうした発見のひとつに足を踏み入れる。今にも崩れ落ちそうな日本
風ディッケンズの世界だ。
「わたしは思い出の修復家です。全力を注いで本を修復して、それがうまくいくと、その本はわたしにとっても思い出になります」
巻いた革が天井まで届いている。棚には染料の瓶や刷毛、革の切れ端があふれている。棚という棚に本がぎっしり詰め込まれてたわんだキャビネット、年季の入った長い作業台の上には仕事に使う道具がなぜかわからない理由できちんと並べられている。職人である達人の整理された混沌だ。
岡野さん(頬がこけて、愛想はあまりよくない)は、ここで完膚なきまでに壊れた本をよみがえらせる。骨の折れる仕事だ。
小さなピンセットを使つて、時には何十年もたったような古い本の折丁をはずす。そして小さなピ
ンクのアイロン(機能すれば何でもいい)折れたページの角を伸ばす。
写真の説明
岡野さんが壊れた古い本、Les Plus Belles Poesies Francaisesを調べる。
岡野さんは、東京の古書店街として有名なこの街で、日本で最も優れた製本家の1人として知られている。
本人はそれは少し違うと考えている。「わたしは思い出の修復家です。全力を注いで本を修復して、それがうまくいくと、その本はわたしにとっても思い出になります」
わたしが岡野さんの扉をたたいたのは、自分自身の壊れた思い出を腕一杯にかかえた客としてだった。それは亡くなった父の蔵書で、The Complete Works of Shakespeare(シェイクスピア全作品解説)とAnna Karenina(アンナ・カレーニナ)とLes PIus belles Poesies Francaises(フランス詩選集)だった。
父はこれらの本を大切にしていた。余白には自分の考えや言葉の意味が書き込んである。戦後まもなく、戦争に負けた日本を後にしてアメリカに渡り、大学で理科の勉強していた頃のものだ。
シェイクスピアは背がとれかけているせいで、表と裏の表紙がぐらぐらしている。小心で酒浸りのフォルスタフのように。トルストイの表紙は継ざ目がまるでネズミにかじられたように長く欠けている。
フランス語の詩集はページがばろぼろでちょっとさわっただけでとれてしまいそうだ。
写真の説明
古い本に新しい命を吹き込むためには、まずそれを壊さなければならない。
岡野さんが黙ってひどい状態の本を仔細に調べている間、わたしは息を殺していた。ページを繰り、背を調べている。それは1980年にリーブルが開設されてから、岡野さんが数えきれない本を直してきた木製の作業台で行われる。
熟考から返ると、岡野さんはひとつ咳払いをし、これからの作戦の段取りを始める。シェイクスピアは、背をはがしてからつけ直しましょう。そのあと表紙を綴じつけ、すべてのページのしわをアイロンで伸ばしてからもとどおりに作り直します。
「ここに少しメモがあるのですが」と、岡野さんが破れた最後のページをさして突然言う。「これは残しましょうか?」
わたしは父が若い物理の学生だった頃、そこに数学の方程式をなぐり書きしていたとはまったく気
がつかなかった。本の命のかけがえのない部分だ。そのページは裏側から目立たないように紙をあてて残してもらうことにした。
「本の作り方も知らずに本を直すなどもってのほかです」
岡野さんはトルストイにはある種の魔法を使う。赤いクロスを探し出してきて表紙の下に敷き、なくなった継ぎ目の代わりする。近くからよく見なければ補修されていることはわからない。
最も難しいのはフランス詩の選集だった。たいへん危ない状態で、完全に崩壊する寸前だった。
岡野さんは本のプレス機に本をはさみ、元の糊をはがし、削ぎ落とし始める。古い本を修復すると
いうよりは、まるで新しい本を作るかのようだ。
最後に山羊革の新しい表紙をかける。「いちばん丈夫でしなやかですからね」と岡野さんは言う。
元の紙の表紙は扉として使われる。
それが適切な解決方法だ。フランスでは、こうした紙表紙の本は、読み終わると伝統的な方法で革表紙に綴じ直され、所有者の書棚に置かれるのだ。
写真の説明
岡野さんによれば、いいかげんな修復は本のためにならないどころか害になる。
リーブルで製本教室を運営し、初歩から製本の技術を教えててきた岡野さんは、本の作り方も知らずに本を直すなどもつてのほかだと言う。
ぼろぼろの本の見かけだけを直すことは、本のためにならないどころか害にしかならない。「製本
家の教科書に『書物の敵』という本がありますが、それによると、
虫、熱、水やほこりなどと同様、製本家自身が本の敵になることもあるのです。中途半端な技術で
本を修復することは、本の寿命を縮めることにもなります」
岡野さんの仕事にはどこかもの哀しさがともなう。どの本も仕事に着手すると自分の本のように思
えてくるのだ。「しかしそれはわたしの本ではありません。手放すときにはいつもすこし寂しい気がしますね」
父の本が岡野さんのもとを去るには今年いっぱいかかりそうだ。込み入った作業である上、その前
にやるべき本が山積している。クリスマス前までには、と岡野さんは約束してくれた。
どんなふうに仕上がつてくるのか、待つのもまた楽しい。
この思い出の修復家の話の後編は、今年末、ジョージ・櫻井がお届けします。
どうぞお楽しみに。
写真:キイチ・カワムラ